学校給食のプロが教える【炒り卵・卵そぼろ】の作り方やポイント!
そぼろ丼 牛乳 みそ汁

甘辛く煮た「肉そぼろ」と、
ほんのり甘い「炒り卵」をのせた
二色丼はこどもに人気な献立。
給食でしばしば登場する

「炒り卵・卵そぼろ」
ご飯の具に入っていたり、野菜に和えられたりと主に名脇役で提供されます。
炒り卵作りは食数にもよりますが、必死にかき混ぜないといけないので、本当に疲れますよね。
そして、たまご料理はシンプルが故に、難しい料理だと、僕自身も感じてますので・・・
今回は学校給食での「炒り卵・卵そぼろ」の作り方について、詳しく解説していきたいと思います。
・鶏卵の特性について
・炒り卵のレシピ内容
・炒り卵の作り方やポイント
炒り卵・卵そぼろ

あなたは卵のこと、どれだけ理解していますか?
美味しい炒り卵を作るためにも、まずは、卵について知ることが大切です。
「炒り卵」と「卵そぼろ」の違いとは?

結論から言わせてもらうと、炒り卵も卵そぼろも同じものになります。
甘い炒り卵もあれば、甘い卵そぼろもあります。
各自、好みで使い分ければ良いかと思います。
僕の勝手なイメージだと、単に「そぼろ」と言ったら、「鶏そぼろ」が強いイメージ。卵そぼろとは普段は言わず、基本、炒り卵と僕は呼んでますが皆さんはどうでしょうか?
そして、両者が合わさると二色丼、そぼろ丼って感じになります。
「そぼろ」とは?

鶏のひき肉や豚ひき肉、たまご等を汁気がなくなるまで炒った料理のこと。
「炒り卵」とは?

たまごに塩やみりん、砂糖などの調味料を入れて混ぜた液をフライパンなどで炒りつけた料理のこと。
上記のことから、
炒り卵 = 卵そぼろ となり、両者は同一の料理と呼べます。
しかし、洋食にこれらの料理に似た料理がもう1つありますよね。
そう、「スクランブルエッグ」です。
ついでにスクランブルエッグについても解説しちゃいます。
「スクランブルエッグ」とは?

鶏卵に乳製品、塩やコショウなどの調味料を加え、かき混ぜながら、半熟状に炒めた料理。充分に火を通す炒り卵と違い、スクランブルエッグは半熟状に仕上げることが多いのが特徴。
鶏卵の特性

鶏卵は加熱すると凝固し、撹拌すると泡立つ性質があります。さらに卵黄には乳化性があり、卵液は粘着性を持つというように部分特有の性質も備えています。上手な卵料理を作るためにも、これらの特性を理解することが大切になってきます。
熱凝固性について
卵白および卵黄は加熱により凝固します。
熱凝固に影響する主な要因
・加熱条件(温度, 時間, 温度上昇速度)
・希釈液の種類(だし汁、牛乳)とその割合
・添加する食品(塩、砂糖、酢など)
・pHの変化
卵黄と卵白の固まる温度帯
| 卵黄と卵白の凝固温度 | ||
| 温度帯 | 卵黄 | 卵白 |
| 58~60℃ | ゼリー状 | |
| 65℃~ | ゲル化が始まる (凝固開始) | 乳白色半透明のゼリー状 |
| 70℃~ | 軟らかく凝固 | |
| 80℃ | 黄白色の粉状に完全凝固 | 白色不透明になり硬く凝固 |
〇〇を入れるだけで、卵がフワフワに!?

卵を加熱すると固くなってしまうのは、卵に含まれるタンパク質が熱によって固く結合してしまうためです。
以下のものを卵に入れることにより、卵のタンパク質に影響を与え、フワフワに仕上げることができます。
■砂糖
■牛乳・豆乳・だし汁
■お酢
■マヨネーズ
【砂糖】
砂糖を入れると、卵の凝固温度が高くなります。結果、タンパク質を固まらせにくくしてくれるので、柔らかいフワフワな卵が作れます。ただし、砂糖を入れすぎるとゲル状で固まりにくくなるので気をつけましょう。
【牛乳・豆乳・だし汁】
卵は牛乳や水分を足すことにより、できあがりが柔らかく仕上がります。 牛乳やだし汁には、微量の塩類や高分子物質を含んでいるので、これらが卵のたんぱく質を可溶化し、結果、熱凝固を促進して食感が良くなり、口当りが滑らかな卵になります。
| たまごの量 | 牛乳の量(豆乳・だし汁でもOK) |
| 1 | 0.3 |
【お酢】
卵にお酢を入れると酸性に傾き、タンパク質の凝固が早まります。さらに、酢の効果で空気を取り込む力が強くなるので、普段よりもふっくらとやわらかい食感の卵に仕上がります。加熱により、お酢が飛ぶので、酢独特の酸味や風味もあまり気になりません。最終的には、お酢の働きでキレイな卵色に仕上がるので、卵料理にはオススメの調味料といえます。
ポイントはお酢の量。多すぎても、少なすぎてもいけません。
| たまごの量 | 酢の量 |
| 30 | 1 |
【マヨネーズ】
卵にマヨネーズを加えると、乳化された植物油や酢が、加熱によるたんぱく質の結合をソフトにし、ふわふわに。しかもこの乳化された植物油は冷めてもかたまらないから、やわらかいままです。さらに、酢のはたらきにより仕上がりもきれいなたまご色に。
美味しい「炒り卵」のレシピ
【炒り卵 1人分の分量 g 】

鶏卵・・・・・・30
油・・・・・・・・1
酢・・・・・・・・1
砂糖・・・・・・・2
塩・・・・・・0.02
作り方と各工程のポイント

それでは、学校給食の炒り卵作りについて、写真付きで各工程ごとに詳しく解説していきます。
①何回に分けて作るか決める

炒り卵は少量ずつ、調理した方が上手に仕上がります。
120Lサイズの回転釜で、鶏卵10〜15kg程
食数・回転釜の設置数やサイズによって、1回で調理する炒り卵の量が変わってきます。
②卵を割る

↑卵を割る割卵セットを用意します。
・割った卵を入れる食缶
・卵を割るカップ
・殻取り用のスプーン
・ゴミ箱

↑片手で卵を割っていきます。
・最初から卵が割れてないか (割れているとサルモネラ菌が繁殖している)
・卵が出血していないか
・異臭がないか(腐ってないか)
・割卵した卵の中に殻が入ってないか
1個ずつ丁寧に見て、食缶に入れていきます。
少量の血なら、加熱すれば問題なく食べられますが、大量調理だと何があるのかわからないので、無難に取り除きます。
③釜を作る

釜全体に油を塗り、うっすら煙が出てくるぐらいまで釜を焼いて、油を馴染ませます。
一度、火を止めます。
あまり、釜を高温にした状態で卵を入れてしまうと、入れた瞬間に底面に焼き焦げが発生し、炒り卵の見た目が悪くなるので注意して下さい。
④釜に卵&調味料を投入

↑釜が熱いうちに、卵を入れます。
釜が熱いときに卵を落とすと、釜と卵の間に水蒸気の膜が出来て、直接、貼り付きにくくなります。
卵を入れる時は、最後まで入れずに必ず少し残します。
理由は殻が底に沈んでいる可能性があるからです。その部分は保存食に回します。
卵を釜に入れたら、すぐに調味料も入れます。
炒り卵作りでは、卵を混ぜることに必死になり、調味料を入れ忘れてしまうという、うっかりミスがありがちです。
完成後に調味料を入れると、浸透圧の関係で、炒り卵から水分が出てきて、パサパサの固い炒り卵になってしまいます。卵を入れたら、すぐに調味料を入れましょう。
⑤火力は外火を弱めにして、内火と中火で作っていきます。
外火が強いと釜肌に卵が貼りつき、焼き色がついた炒り卵になったり、焦げが入る原因となるので注意が必要です。
中火〜強火の間ぐらいの火加減が理想です。
※卵が固まり始めてからも、弱火でチンタラやってると、卵が変色してしまいます。
※卵10kgの炒り卵を作るのに要する時間は、釜に卵を入れてから、8〜10分程です。
混ぜ方は?
基本的には、部分的に細かく小さくまぜることを意識します。
小さく混ぜることで混ぜる回数は増えますが、同じ場所に力が集中しにくく、早く混ざり合わせることができます。たまに全体を大きく混ぜます。
↑これぐらいで火を止めて、中心温度を取ります。

↑余裕で温度がいってます。
卵白、卵黄の凝固温度は80℃なので、この時点で80℃は必ず達温してます。給食では温度確認が必須なので、必ず中心温度を取りましょう。

↑温度が確認できたら、釜内で軽く混ぜて、ボールやタライに急いで引き上げます。
炒り卵の色が変色してしまう理由
卵の加熱温度が高く、加熱時間も長くなると、「硫化水素」という無機化合物が発生します。
硫化水素は卵黄の鉄分や釜から出る鉄分と化合して硫化鉄(黒色)となるため、結果、炒り卵が暗緑色に変色していきます。
⑥タライやボールに引き上げる。

↑タライやボールを多めに用意して、なるべく小分けにして、手早く冷ます。
※たまごが熱いうちは、たまご同士がくっつきやすいのと、衛生面からも冷ました方が良いからです。

↑ホイッパー等でほぐしながら、冷ましていきます。
⑦粗熱がなくなれば、完成
まとめ

いかがでしょうか。今回は炒り卵作りについて解説させていただきました。
最後に上手な炒り卵作りのポイントをまとめてみます。
(無理して、いっぺんに作らない)
・規定量の酢を入れる。
(ふっくらキレイな卵色に仕上がる)
・火加減は中火〜強火で細かく小さく混ぜる。
(外火が強いと焦げの原因になる)
・卵が固まってからは時間をかけない。
(硫化水素が鉄に反応して、変色するため)
・完成後は小分けにし、粗熱をとりながら、ほぐす。
(熱いと卵同士がくっつきやすい)
↑こちらの5点のポイントを知るだけでも、炒り卵作りで失敗する可能性はグ〜ンと下がるかと思います。
たかが、炒り卵ですが、されど炒り卵です。
僕は長く、学校給食の仕事に携わってきてますが、炒り卵作りで、泣きを見る調理員さんの姿をたくさん見てきました。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました!









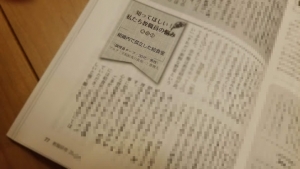











最近のコメント